都会での生活から環境を変えて、地方に移住をする方が年々増加しています。
自然が多いことや自分らしく生活できるメリットは魅力的だと思いつつも、移住の費用がどのくらいかかるか不安に思うでしょう。
本記事では、移住の初期費用がどのくらいかかるのか、また費用が少しでも安くなるような方法や使える助成金について、解説していきます。
移住の第一歩として旅館・ホテルで働くのもオススメ!
【旅館やホテルで働くメリット】
・働きながら地域の人との交流が深められる
・旅館・ホテルで働く=住居もセットで決まる
・初期費用や生活費が抑えられる
移住によってかかる費用とは?初めてでも安心の基準も合わせて解説

移住にかかる費用がどのくらいかかるのかは、移住先や家族構成などによって異なります。
一般的な費用や、費用の詳細について解説していきます。
- 住むまでにかかる費用
- 住んでからかかる費用
- 1人暮らしの場合の費用
- 家族で移住する場合の費用
それでは、一つひとつ見ていきましょう!
費用1|住むまでにかかる費用
移住にかかる一般的な費用は60万円〜100万円ほどといわれています。
ただし、家族構成や移住時期、車が必要かどうかなどで変動するため、具体的に算出していくことが大切です。
①引っ越しまでの下見費用
地方移住を検討している際には、下見をすることをおすすめします。
どんな立地でどんな利便性があるのか、実際に足を運んで見てみることで、移住時の想像がつきやすくなることや、どんなデメリットがあるのかを知って対策をとることができます。
また移住に力を入れている地方自治体は、お試し移住制度や移住体験ツアーなどを提供しており、助成が受けられる場合があるため、問い合わせてみるとよいでしょう。
②引っ越し費用
引っ越し業者に見積りをとりましょう。
輸送する荷物の量や大きさによって異なり、3〜4月の繁忙期には高くなります。
また、片道900kmを超える長距離輸送となると、さらに値段が上がります。
③住居の初期費用
新居の購入・賃貸どちらにしても、不動産仲介業者を利用する場合には、仲介手数料がかかります。
賃貸の場合、敷金・礼金・前家賃・火災保険料などを含めると、家賃の4〜6倍かかると見積もってよいでしょう。
物件を購入する場合には購入費、または住宅ローンを組む場合には頭金が物件価格の2割程度の金額がかかり、そのほかに登記費用や保証料がかかる場合があります。
費用2|住んでからかかる費用
住んでからは、食費・水道光熱費・通信費などの生活費がかかります。
地域によっては追加で購入する暖房器具や、自動車を購入する場合には購入費用と駐車場代がかかります。
その地域ごとに必要となりそうなものを、下見の段階でリストアップするとよいでしょう。
費用3|1人暮らしの場合
単身で地方移住をする場合には、おおよそ26〜60万円かかると見積もりましょう。
引っ越し費用は前項でお話したとおり、繁忙期かどうか、また長距離かどうかでも変わりますが、3〜4月の繁忙期では多くて18万円程かかります。
賃貸費用も同様に、繁忙期かどうかで変わります。
費用4|家族で移住する場合
例えば3人家族が引っ越しをする場合、おおよそ87〜125万円ほどかかると見積もってよいでしょう。
人数が多くなる分荷物も多くなり、引っ越し費用が高くなります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上が、移住にかかる費用でした。
- 住むまでにかかる費用
- 住んでからかかる費用
- 1人暮らしの場合の費用
- 家族で移住する場合の費用
続いて、移住して変化する支出を紹介します!
移住して変わる支出とは?注意しておきたい費用も解説!

都心での暮らしから地方に移住すると、変化する支出があります。
- 家賃・住宅費
- 光熱費
- 移動費
- 食費・日用品費
- 税金
それでは、一つひとつ見ていきましょう!
支出1|家賃・住宅費
家賃や住宅費は、地方は圧倒的に安く抑えられます。
地方の家賃相場は都会と比べて1/2〜1/3くらいまで安く、住宅用地の相場は1/10以下であるため、地方は持ち家率がかなり高いことが特徴です。
支出2|光熱費
光熱費全体は、1年あたりで計算をすると、さほどかわりません。
ガスは都市ガスから、プロパンガスに変わります。
都市ガスは月額で利用料がかかるのに対して、プロパンガスは1本あたりの金額になり、都市ガスよりも高くはなりますが、利用する頻度によっては都市ガスより安くなる可能性があります。
水道費は地域によって基本料がかわりますが、都心と変わらないところが多いです。
場所によっては自宅から近いところで湧き水や地下水が湧いているところもあり、汲んでくることで水道代を安く済ませることもできます。
特に地方は冬が寒いため、冬の暖房費が都心よりかかりやすい傾向にある一方、夏は都心ほど暑くなく冷房代は抑えられるため、電気代は1年を通すとさほど変わりません。
支出3|移動費
都会では電車やタクシーでの移動が簡単にできますが、地方では駅と駅の間が遠く、電車の本数も多くなく、タクシーは繁華街以外はほとんど走っていません。
そのため車やバイクでの移動が必須になるでしょう。
車を新たに購入する場合には、購入費・保険料・税金・駐車場代などがかかり、おおよそ50〜70万円ほど必要となります。
ガソリン代は都会より地方のほうが高い傾向にあります。
支出4|食費・日用品費
食料品は都会よりも地方の方が安い傾向にあります。
地産地消に取り組んでいる地域は野菜が比較的安く手に入ります。
また移住後の近所づきあいが良くなれば、お互いのものを交換しあうこともできるでしょう。
支出5|税金
全国的に、住民税は都心と比べて地方の方が高い場合が見受けられます。
その差は数千円程度であり、すごく高いわけではありませんが、一部の地方自治体には独自の課税制度が存在する場合があるため、確認が必要です。
移住先の自治体によっては、今までよりも税金が高くなることを認識しておきましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上が、移住で変わる支出でした。
- 家賃・住宅費
- 光熱費
- 移動費
- 食費・日用品費
- 税金
続いて、移住の際の注意点を紹介します!
移住の際の注意点

移住時には多くのやるべきことに追われて、意外と忘れてしまうことがあるため、以下で解説をしていきます。
- 仕事
- 移住相談と移住が年度をまたぐ場合
- 選んだ地域に馴染めるか
それでは、一つひとつ見ていきましょう!
注意点1|仕事
新しい職種に就職しようと考えている方は、移住前から仕事を探し、決まった状態で移住をすすめていくようにしましょう。
地方移住をしてから仕事を探すとなると、見つかるまでは貯金を切り崩して生活することとなります。
移住そのものに経済的な負担がかかることは避けられないため、できるだけ早いタイミングで収入を得られる状態を作っておくことが大切です。
また、現時点でリモートワークをしていて、地方移住でもそのまま続けようと思っている方は、定期的な出社など、
注意点2|移住相談と移住が年度をまたぐ場合
移住時の支援金や補助金は、年度ごとに設けられている場合が多くあります。
そのため、年度をまたぐと廃止になってしまうものや、条件内容や金額が変更になる場合が存在します。
移住を相談していた時期に使おうと思っていたものが移住時で使えるかどうか、年度をまたぐ場合には、移住相談窓口の担当者に確認しましょう。
状況を確認しながら計画を立てていくことが大切です。
注意点3|選んだ地域に馴染めるか
文化や考え方が多種多様である東京と比較し、地方にはその場所ごとに慣習や文化・しきたりなどがあります。
経験したことがない慣習に、移住後に馴染めるかどうか、あらかじめ調べておくとよいでしょう。
地方自治体には、2週間〜2か月など期間限定で移住できるおためし移住制度や、移住体験ツアーを企画しているところがあります。
またこれらを利用することで、移住後に助成金がでる自治体もあります。
事前に体験をしていくことで、移住後の生活の想像がつきやすくなることもメリットです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上が、移住の際の注意点でした。
- 仕事
- 移住相談と移住が年度をまたぐ場合
- 選んだ地域に馴染めるか
続いて、移住の初期費用をおさえる工夫について紹介します!
移住の初期費用を抑えるためには?

移住の初期費用を抑えるためには、工夫をしていくことが必要です。
- 引っ越しの繁忙期を避ける
- なるべく荷物を減らす
- 複数の引っ越し業者から見積りをとる
- 無料で住める家
- 仕事の都合で家がついているものを選ぶ
それでは、一つひとつ見ていきましょう!
工夫1|引っ越しの繁忙期を避ける
就職や入学に伴う引っ越しとなる12月〜4月あたりの需要が高まり、特に3〜4月が繁忙期で、引っ越し料金が数万円高くなります。
繁忙期は特に、引っ越しの希望の時間帯を指定することも難しくなります。
余裕を持った移住を検討する際には、繁忙期を避けて設定するとよいでしょう。
工夫2|なるべく荷物を減らす
引っ越し時の荷物が多いほど、使用するトラックの大きさや数が多くなるため、その分値段が上がりやすくなります。
大型の家具が無いだけでも、数万円は安くなるでしょう。
できるだけ、持っていく荷物を減らすことをおすすめします。
とはいえ、引っ越し前にごみとして破棄をして、引っ越し後に現地で新品を買うと、それなりに費用がかかってしまいます。
新品のものにこだわらなければ、中古のものがフリマアプリで販売・購入できたり、タイミングがよければ地域密着アプリで無料で引き渡し・引き取ることも可能です。
SNSを駆使して引き取り先を見つけるなど、工夫をして荷物を手放していきましょう。
工夫3|複数の引っ越し業者から見積りをとる
引っ越し業者によって、サービスや強みが異なります。
複数の引っ越し業者から見積りをとり、検討している業者へ、他社の値段を提示することで、安い金額へ交渉することができます。
工夫4|無料で住める家
地方には都心と比較して空き家が多くあり、所持しているだけで税金や維持費がかかってしまうため、収入にならなくても手放したいと思っている方が多くいます。
条件や交渉次第で、無料で譲ってもらえる可能性があるため、検討してもよいでしょう。
ただし、内装の修繕や改装、残存物の撤去などが必要になる場合があります。
見積りをとりながら比較していきましょう。
詳しくはこちらの記事にて解説しています。併せてご覧ください。
工夫5|仕事の都合で家がついているものを選ぶ
地方移住とともに仕事を変える場合には、寮や住まいがついているものを見つけてみましょう。
仕事先が所有している物件であれば、寮や住まいの費用補助だけでなく、水道光熱費も含まれているものもあります。
物件を選ぶ手間も省けるため、より手軽に地方移住を始めたい方にはおすすめです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上が、移住の初期費用をおさえる工夫でした。
- 引っ越しの繁忙期を避ける
- なるべく荷物を減らす
- 複数の引っ越し業者から見積りをとる
- 無料で住める家
- 仕事の都合で家がついているものを選ぶ
続いて、移住の際に使って良かった助成金を紹介します!
地方移住して使ってよかった助成金とは?

地方移住時に少しでも経済的に余裕がでるような、おすすめの助成金を紹介します。
- 移住支援金
- 自治体が用意する支援制度
それでは、一つひとつ見ていきましょう!
助成金1|移住支援金
内閣府が推進している事業であり、東京23区に在住または通勤をしている方が地方移住をする際に支給をもらえる制度です。
各地方公共団体が主体となっているため、それぞれによって条件や支給額が変わってきます。
詳しくはこちらの記事にて解説しています。併せてご覧ください。
助成金2|自治体が用意する支援制度
移住支援金は、国と地方自治体が協力して支援を組んでいることに対し、各自治体が独自で用意している支援制度もあります。
住宅への支援、就業に関する支援やお祝い金、結婚・出産・子育てに関する支援などがあり、各自治体によって強みが異なることが特徴です。
移住先の候補がいくつか挙げられたら、その自治体での支援制度がないか探してみるとよいでしょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上が、移住の際に使って良かった助成金でした。
- 移住支援金
- 自治体が用意する支援制度
移住費用を計算して計画的にすすめていきましょう

今回は、移住の初期費用がどのくらいかかるのか、また費用が少しでも安くなるような方法や使える助成金について、解説してきました。
初めての移住では、移住してみて初めてわかることも多く、予想していなかったことが起こることもあるでしょう。
あらかじめ初期費用を算出しておくだけでなく、予想外の出費があった際に対応できるように、見積もって計画をたてていきましょう。
移住の仕事探しと住まい探しは『ローカルック』
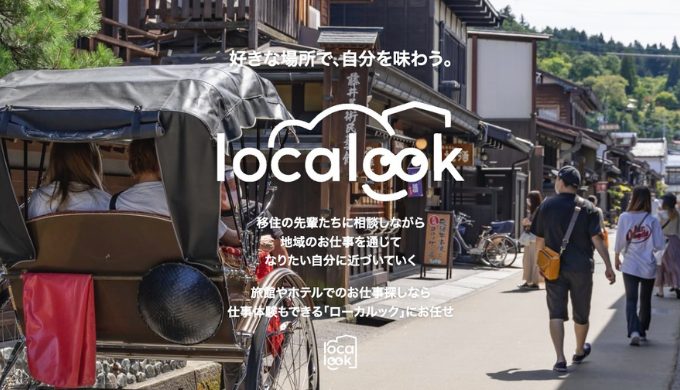
地域のお仕事を通じて 「移住の第一歩を応援するサービス」です。
「好きな場所で、自分を味わう。」をコンセプトに魅力あふれる地域、そこで暮らす人たちとの出会いのきっかけを「ローカルック」が生み出していきます。
『移住をしてみたいけど、何からはじめればいいかわからない。』『移住するための仕事探しの方法や住まいの探し方がわからない。』などなど、移住についてお悩みの方は、まずはLINEで質問してみましょう。


